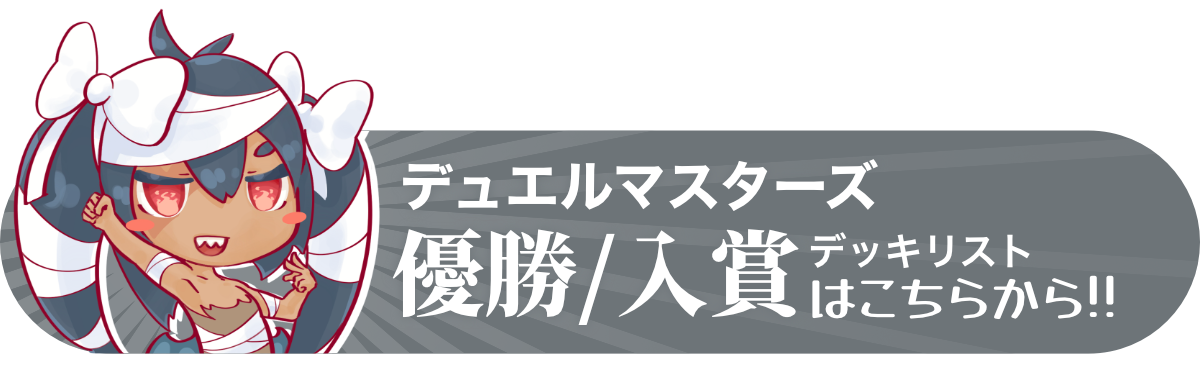最近「オーバーガードZは手に刺さるから痛い、痛すぎて相互シャッフルできないので使うのをやめてほしい」という意見を時折耳にします。
色々と心配になってしまう意見なのですが、こうした意見を耳にするたびに
「そういえばスリーブやシャッフルのことって、どうやって学べばいいんだろう」などと考えてしまいます。
とても大切なことなのに、誰かに教えてもらう以外で知る手段ってあんまりないですよね。
ここ最近、私自身がこうしたことを周囲のプレイヤーにレクチャーする機会が何度かありました。そこで教えたことをみんなが読める記事の形で残しておくと便利だろうと思い、今回の記事を執筆いたしました。
今回の記事は、シャッフルの方法、スリーブの装着方法といった一番初歩のところはスキップして、その少し先の「TCGを長く続けていくうえで知っておかねばならないこと」を色々と紹介させていただく記事となっています。
ちょっとアドバンスドな基本の話を、楽しみつつ知っていただければうれしいです。
手に刺さるスリーブ、オーバーガードZ
「オーバーガードZは手に刺さるから痛い、痛すぎて相互シャッフルできないので使うのをやめてほしい」という意見を時折耳にすることがあります…という話は冒頭でしましたね。
実際、オーバーガードZは手に刺さります。
はじめてオーバーガードZというものに出会ったのは、10年くらい前のことだったでしょうか。当時の自分はデュエマ専のプレイヤーでした。その頃に仲良くなったプレイヤーがオーバーガードZを使用していたのですが、それが本当に痛くて痛くて…びっくりしました。
オーバーガードZは本当に硬くて分厚いスリーブで、角もとがっているので、そこが手に刺さるんですよね。
当時はデュエルマスターズ公式スリーブも旧規格であり、フニャフニャでガバガバ、非常にやわらかい造りのものでした。そういうこともあって、硬いスリーブには全然慣れていなくて、オーバーガードZの痛さはなおさらに衝撃的でした。
「こんな痛いスリーブ、自分は絶対に使わないぞ」などと当時は思ったことでしたが、紆余曲折あって今は愛用しています。
「オーバーガードZが痛いスリーブなのではない」ということが分かったからです。
オーバーガードZ
株式会社やのまんが発売している、ものすごく分厚くて丈夫なオーバースリーブ(通常サイズのスリーブのさらに上から装着するスリーブ)。コアなファンが多いことでも有名。
やや薄い「オーバーガードZL」というバリエーションもありますが、行きつけのショップで店員から「絶対買うな」と言われました。それでも買ってみたのですが、そういう感じの品質でしたね…
オーバーガードZが痛い…のはちょっとマズい
オーバーガードZが痛いのは、シャッフルの最中にバリ硬のスリーブ角が手のやわらかい部分(手のひら、具体的には母指球筋群と小指球筋群、手指低球)に刺さるからです。
球筋は丘になっていてカードと接触しやすい。
これは、逆に言えば、シャッフルしているプレイヤーが手のひらをスリーブ角に
「痛みを感じるほどの強さで」押し当てている…ということでもあります。
むしろ、このように表現するほうが妥当でしょう。シャッフルという行為の主体はプレイヤーだからです。
オーバーガードZが自らの意思で手に突き刺さって、人々に痛みを与えているわけではありません。
この「痛みを感じるほどの強さで」スリーブ角に手を押し当てている…というのは、ちょっと問題な行為です。
オーバーガードZを手に押し当てて痛みを感じるのは、オーバーガードZが硬いからであり、硬いがゆえに手を押し当てられても角が折れないからであり、折れないために角が手に刺さるからです。
となると、「痛くない」のはどういうときなのか。
オーバーガードZなら痛いけど、他のスリーブなら痛くないというのは、どういうことなのか。
もはや皆まで言わなくてもいいとは思いますが、
「手を押し当てて柔らかいスリーブの角を折っているとき」ですね…
手のひらをスリーブの角に押し当てても、柔らかいスリーブであれば角が折れ曲がる、折れ曲がるから刺さらない、刺さらないから当然痛くない。
「柔らかい~から痛くない」としましたが、オーバーガードZで痛みを感じている人は、普通のスリーブをシャッフルする時にもちょっとだけチクチクしているんじゃないでしょうか。
そして「スリーブとはチクチクするものなのだ」と思い込んでいるかもしれませんが、実はそんなことはありません。正しい手順でシャッフルをすればチクチクしないものなのです。
痛くないヒンズーシャッフルの持ち方例。人差し指をデッキの上底へ、親指を右側面、残り三指を左側面へあてるとデッキの四隅が手のひらに刺さらない。指がカード面と垂直に交わるため、指の長さを無駄なく使ってデッキをホールドできる。分厚いデッキでも持ちやすい。
スリーブ角を折っちゃうのはマズい
スリーブの角を折り曲げてしまうと、その折り目が残ってしまうことがあります。
折り目が残ったスリーブは、競技度の高いイベントではマークド扱いされて反則となってしまうこともあります。競技度の低いイベントであっても、折り目の程度が酷ければマークドの疑いが生じてしまうため、使用がためらわれるでしょう。
マークド
何かしらの印がついていて、裏面からでも識別できる状態になっているカード。故意に印がつけられたものに限らず、不慮の出来事で判別できる状態になったものもマークドとされることがある。
それが自分のデッキの自分のスリーブだったとしても問題なのですが、それが対戦相手のものだったならますます問題です。対戦相手のスリーブを使用できない状態にしているわけですからね。
「オーバーガードZを痛いと感じるシャッフル」は「手のひらをスリーブ角に押し当てるシャッフル」であり、「スリーブ角を折るシャッフル」でもある、ということを覚えておいてください。たとえばトランプやUNOで遊ぶ時なら、そういうシャッフルでも問題ないとは思いますが、TCGを遊ぶとなると話は別です。
硬いスリーブが痛いと感じたら、そのスリーブに腹を立てるよりも前に、自分のシャッフルを疑ってみてください。
お互いのカードやスリーブを大切にするために、手のひらを角に押し当てないシャッフルを習得することが大切です。TCGを長く遊んでいく以上、シャッフル技術の向上は不可欠です。
最近はYoutubeなどで分かりやすくシャッフルの手順が紹介されているので、そういうので勉強してみてください。
カードゲーマー必修科目『ファローシャッフル』についてよく使う3種類を紹介します
動画がいいなと思っていただけたら高評価ボタンを押してください!動画制作のモチベーションになります!そして少しでも面白いなと思っていただけたらぜひ【チャンネル登録】をよろしくお願いします!※デッキリストの送り先はTwitterのDMまでお願いします!リジェのTwitter https://twitter.com/r...
なお、自分のシャッフル技術に自信のない間は、相互シャッフルの際に、相手デッキのシャッフルを省略させてもらう(カットで済ませる)という選択肢もあります。
相互シャッフルをカットで済ませたりすると、「相互シャッフルで相手がシャッフルする分も加味して少なくシャッフルしたのだから、そちらがシャッフルしてくれないと十分に山札が無作為化されない」などというプレイヤーが稀におりますが、「相手のシャッフルの有無によって無作為ではない(≒作為的である)配列が生じ得るシャッフル」というのが仮にあったとして、それは山札の無作為化にはなっていないですよね…
などと理屈を言ってもカドが立つだけですから、自分の分までしっかりシャッフルしてもらえるよう、丁重にお願いするのがよいでしょう。
オーバーガードZの罠
「罠」と書きましたが、別にオーバーガードZの品質を酷評するわけではありません。
ただ、オーバーガードZは非常に個性的な製品なので、扱いに注意が必要なのです。
それで、具体的にどのような注意が必要なのかというと、
「中に入れるカードよりもオーバーガードZのほうが頑丈である」ということです。さらにいえば、内側のレギュラーサイズスリーブよりも頑丈です。圧倒的に。
「それは良いことじゃないのか」と思われるかもしれません。実際良いことではあります。この頑丈さがオーバーガードZ使用の最大のメリットですからね。
ですが、これが問題を起こすこともあるんです…
オーバーガードは、中のカードやスリーブよりも頑丈でしなやかです。そして一番外側に装着されます。だからプレイヤーが直接触れるのはオーバーガードZであり、プレイヤーはオーバーガードZの頑丈さ、しなやかさに触れ続けることになる。
すると、どうなるか。
プレイヤーたちは次第に内側のカード/スリーブの感触を忘れていくわけです。オーバーガードZよりも圧倒的に脆い内側の感触を…です。
オーバーガードZの頑強さしなやかさにまかせて、はげしい「絞り」やシャッフルをやるように癖づいてしまう人もいます。するとどうなるのか…オーバーガードZはなんともないのに内側がダメになっている、ということが生じるわけですね。大事なレアカードが折れていたり、お気に入りのキャラクタースリーブにシワが入っていたり…
絞り(スクィーズ)
カードをテーブルに押さえつけ、端の方からカードをしならせながら捲っていく操作。無意識にやっているカードゲーマーは多いが、カードが激しく損耗するのでやってはいけない。バカラでは演出としてディーラーやプレイヤーが「絞り」を行うことがある。
内側が耐えられないほどの負担にも、オーバーガードZは耐えられてしまうがゆえに、こういうことが生じてしまうわけです。
オーバーガードZを使用する際には、内側のカードやレギュラースリーブの脆さを意識して、その脆さにあった丁寧さでカードをあつかう必要があります。
もっと言えば、オーバーガードZを使用する/使用しないに関わらず、カードやスリーブの脆さを意識することはとても大切です。最近はオーバーガード並みに頑丈なスリーブが増えていますしね。
対策
定期的に普通の厚さ、普通の硬さのレギュラースリーブ(たとえばKMCハイパーマット)だけを装着したデッキを使用する機会をつくるのも有効な対策です。そうすることで、オーバーガードZの内側にあるカード/スリーブの脆さを思い出すことができます。
デッキを回し終わったら、レギュラースリーブを観察してみましょう。変なシワがスリーブに入っていたら、オーバーガードZの影響でカードの扱いが荒くなっている危険なシグナルです。
カードを曲げすぎていないか、絞りの癖が付いてはいないか、自分のカード操作を見直すようにしましょう。
カードの強度を手で確かめる
デッキを速やかに操作する技術を磨いていくうえで、カードの「コシ」を使って、カードを適度にしならせる技術は不可欠です。
カードのコシ
紙が持つ反発力や弾力性のことを「紙のコシ」と言います。紙の剛性としなやかさのバランスと言ってもいいでしょう。コシが強い紙は折り曲げようとしても平面に戻る力が強く働きますが、コシが弱い紙はあっさり折れ曲がってそのまま戻らなくなってしまいます。カードも紙でできているのでコシがあります。そのコシの強さがシャッフルなどの操作の力加減において重要になります。
「カードをどこまでしならせていいのか」を手で理解し、無意識的に最適なしなりを作れるようになれば、あらゆるカード操作がスムースになり、誤った操作でカードを傷つけるリスクも小さくなります。
スピーディかつ安全なカード操作を身につけるために、カードの「コシ」を手で確かめておくとよいでしょう。
では、具体的にどうすればいいのか。
手っ取り早いのは、スリーブを付けていない裸の状態のカードを触ることです。
不要なカードを40〜60枚(デッキの枚数)束ねて、いろんなシャッフルをガシガシやってみる。ヒンズー、ファローはもちろんリフルシャッフルもやってみればいいでしょう。
(絶対に不要なカードでやってください。特にリフルシャッフルは)
リフルシャッフル
山札を二つに分け、激しくしならせながら噛み合わせていくシャッフル。遊戯王の漫画の名言「ショットガンシャッフルはカードを痛めるぜ」のショットガンシャッフルは、このリフルシャッフルのこと。本当にカードを痛めます。
そうすると、カードがどれだけのコシを持っていて、どれだけの乱暴な操作に耐えるのか、どれだけのしなりに耐えるのかということが肌で感じられるはずです。
毎日裸のカードをガシガシ触っていれば、適度にしなりを使ったカード操作というものが次第に身についてくると思います。
スリーブの強度を手で確かめる
一言で「スリーブの強度」といっても、いろんな指標があります。
ひとつは剛性、スリーブの硬さです。
もうひとつが擦り減りにくさ、使っているうちに摩滅してしまわない丈夫さです。意外にも摩擦に弱くて長持ちしないスリーブは多いのです。
最後に裂けにくさ、これも大事な指標です。
ここからは余談なのですが、地元のショップの店員にスリーブの強度を実演してくれる人がいて、その人がいろいろなスリーブを裂いたり揉みしだいたりして見せてくれたのを覚えています。その時からスリーブの「裂けにくさ」という指標を意識するようになりました。一時期話題になったシャッフルマスターもやってもらいましたが、あれは本当に裂けにくいみたいですね。
とりあえず、スリーブの剛性(硬さ)を知りたい場合は、先に紹介したように普通の厚さ、普通の剛性のレギュラースリーブだけを装着したデッキを使用する機会をつくるのが一番です。
何も入れていないレギュラースリーブだけを揉んだり曲げたりしても意味がない…ということはありませんが、スリーブはカードとニコイチで使うものですから、装着した状態での感触が大事なのかなと思います。
もっともっと手っ取り早い方法で
先ほど「裸のカードを毎日ガシガシシャッフルする」という方法を紹介しましたが、もっともっと手っ取り早くカードのコシを理解する方法があります。
それは、カードを折ることです。
※もちろん、不要なカードを、です。大切なプレイ用カードでは絶対に絶対にやらないでください。
MTGでは
「ベンドテスト」というのが知られていますが、あれのようにカードを曲げてみるのです。
ベンドテスト
MTGカードの真贋判定方法のひとつ。カードの上下部分を持って、カードの上下辺が触れ合うまでゆっくりと曲げていく。本物は折れてしまわないとされているが、MTGカードの紙質は不安定で、本物でも折れてしまうことがある。大事なカードでやるのは絶対厳禁。
カードが折れ曲がる直前に加えていた力が、カードが耐えられる限界ギリギリの力ということになります。わかりやすいですね。
MTGやデュエマでは、カードの上下辺が触れ合ってもカードが折れないことが多いです(だから「ベンドテスト」というものがあるわけですが)
ただし、それで折れなかったとしても、カードの内側にダメージが蓄積されることには注意してください。仮にもとの平面に戻ったとしても、完全に無傷というわけではありません。
また、最近のMTGカードは紙質が不安定で、正規品であってもベンドに耐えない場合があります。SecretLair製品にも極端に曲げに弱いものがあります。
そういうことも加味しつつ、何枚かベンドしてみると(MTGおよびデュエマの場合は)無傷で曲げられるのは(大きく見積もって)10度まで、ということがわかって来ると思います。
柔よく剛を制すが、柔らかすぎるカードはやっぱり折れる
自分がやっているTCG以外のカードもベンドしてみるとよいでしょう。
特にポケモンカードのベンドは勉強になります。
ポケカのカードを実際にベンドすると歪むのですが、実はポケモンカードはしならせる操作全般に弱いのです。
なぜなのか。
実はポケカのカードは、他のTCGと比べて非常に薄いのです。手の小さい子供が60枚のデッキをつかんでシャッフルできるように…という配慮でしょう。
この薄さがポケカ界隈の諸々のトラブルの元凶になっています。
まず、ポケカ界隈では異様にシャカパチ(ハンドシャッフル)が嫌われているのですが、これはうるさいからではなく(うるさいのもあるかもしれませんが)、
シャカパチするとカードがガタガタになるからです。シャカパチはカードをしならせる操作なのですが、ポケモンカードは薄すぎて「しなり」に耐えられません。
金銭的に余裕がある方は、ポケカのデッキでリフルシャッフルをしてみてください。…いや、そんなことのためにデッキを買うのはもったいないので、やっぱりやらなくていいです。
まあ、とにかく、ポケカデッキでリフルをやると一撃で60枚全部が歪みます。一回のリフルにも耐えないカードですから、尋常な程度(10度以内)のしなりであっても、繰り返し曲げているうちにどんどん歪んでいきます(一時期ポケカをやっていたので体験しました)
ポケモンカードにおいて、ファローシャッフルや相互シャッフルを嫌がるプレイヤーが他より多く見られるのも、この「カードの薄さ」も関係していそうです。
そもそも薄くて折れやすいカードを相手に預けたくない。そういう心理が無意識的に働いているのでしょう(ジムバトルあたりでは、ファローシャッフルができないプレイヤーが多いという事情もありますが)
分厚いカードはどうなるのか
それでは、逆に硬くて分厚いカードはどうなるのか。
やっぱりコシが足りなくて、折れるんですよね…
論語に柔能制剛(柔よく剛を制す)というのがありますが、まさにその通りで、ただ硬いだけでは折れてしまいます。薄くてやわらかいポケカもガタガタに歪んでしまうわけですが…
カードの(紙の)コシは、紙のバランスによって成り立つものです。紙の縦横の長さと厚さのバランス、剛性としなやかさのバランス、そういうものが絶妙に調整されてコシのある紙になる。
色んな厚みのカードを曲げてみることで、カードのコシというものがより深く理解できるようになると思います。
なぜファローシャッフルが必要なのか
シャッフルにはいろいろな種類があるわけですが、それぞれシャッフルごとにカードの位置の移動の仕方に特徴があります。
最も頻繁に使用されるヒンズーシャッフルには、カードの山札内での位置が大きく上下しやすい性質があります。ですが、手で掴んだひとかたまり単位でカードが移動するため、隣接するカードとの位置関係が変化しずらいという欠点もあります。ゆえにヒンズーシャッフルだけでは、山札の配列を無作為化しずらいのです。
ヒンズーシャッフルでのカード移動イメージ。山札内の位置が大きく変化するが、隣接するカードの位置関係が変わりづらい。
ヒンズーシャッフル
トランプなどで使用されるシャッフル。カード束の下から数枚カードを抜き取り、それを束の上に置く、という操作を何度も繰り返す。ほとんどの人にとって最もなじみ深いであろうシャッフル。
その一方で、ファローシャッフルは、デッキトップ付近のカードの位置が変化しづらい反面、隣接するカード同士の位置関係が変化しやすいという特徴があります。
ファローシャッフルでのカード移動イメージ。山札内での位置はほとんど変化しないが、隣接するカードどうしの位置関係が変化する。画像は一回目のシャッフル。
ファローシャッフル
山札を二つの山に分け、二つ山のカードが大体交互になるように嚙み合わせるシャッフル。横入れシャッフルと呼ばれることもある。
つまり、ファローシャッフルは、ヒンズーシャッフルとは真逆な性質を持っているわけです。両方のシャッフルを交互に行えば、お互いの欠点を補いあうことになり、比較的短い時間で無作為な山札をつくることができます。
そういうわけで、競技度の高いイベントでは
「ヒンズーシャッフルだけではいけない、ファローシャッフルも必要」とされるわけですね。
パーフェクト・シャッフルの規則性
「パーフェクト・シャッフル」というのは、山札をふたつの束に等分し、それぞれの束から丁度一枚ずつ交互に重ねていくシャッフル方法。あるいはそれを完全に行う技術のことです。
リフルシャッフルのほか、熟練の技術があればファローシャッフルでもパーフェクト・シャッフルを行うことができます。
パーフェクト・シャッフルには、
「一定の回数シャッフルを行うことと、最初にシャッフルを行う前の配列に戻る」という性質があります。
なお、初期配列に戻るまでのシャッフル回数は、山札の枚数に応じて変わります。例えば、トランプの枚数52枚では8回のパーフェクトシャッフルで初期配列に戻ることが知られています。
もちろん、TCGで一般的にされるファローシャッフルはパーフェクト・シャッフルではないのですが、パーフェクト・シャッフルの規則性を知っておくことはファローシャッフルの性質を理解する助けになるのではないかと思います。
パーフェクトシャッフルの性質を視覚化する
パーフェクトシャッフルによる各カードの動きを、表計算ソフトで視覚化してみます。
この手の計算は複雑そうに感じるかもしれませんが、表計算ソフト(SpreadSheet)で、しかもVLOOKUP関数だけで簡単にできてしまいます。
シートをグーグルドライブで共有しているので、気になる方はぜひご覧ください(
共有リンク)
C列のセルが初期配列のカードを表しているのですが、ここの数字を変更すると表全体に適用されます。何かしら別の検証に活かせるかもしれません。
確認のための52枚
まずは、52枚(トランプの枚数)でやってみます。
先述したとおり
「52枚ではパーフェクト・シャッフル8回で初期配列に戻る」ということが一般的に知られています。
このシートでも8回目に初期配列に戻ったならば、このシート上の関数が正常に機能していることの確認になるはずです。
画像タップで拡大できます(領域外をタップで拡大を解除)
スクリーンショットなので端の方が見切れてしまっています。下の方まで確認したい方は、
こちらからスプレッドシートをご覧ください。
赤いセルが初期配列でトップ側だったカード、青いセルがボトム側だったカードです。
8回目のシャッフルでしっかり初期配列に戻っていますね。
おそらくシートの関数は正常に機能しているだろう、ということで60枚、52枚のパターンを確認していきます。
60枚(MTG、ポケカ)
MTG、ポケカなど山札が60枚のパターンです。
58回目のシャッフルで、最初(0回目)の配列に戻ることが確認できます。
シャッフル回数が少ない間は、山札トップ側のカードはトップ側に、ボトム側のカードはボトム側にとどまりやすいという傾向も確認できますね。
先述したとおり、ファローシャッフル=パーフェクト・シャッフルというわけではありません。ですが、ファローシャッフルがパーフェクト・シャッフル可能な種類のシャッフルである以上、一定以上の精度で行われたファローシャッフルにも上と同様の傾向が現れるものと予想されます。
実際に、この傾向を悪用した不正行為も存在するので、そうした疑いを抱かせないためにも、シャッフルはファローだけでなくヒンズーもあわせて行うことが大切です。
低精度の不正行為
そもそも
積み込みなどの不正行為は「確実に〇〇を引く」といったものばかりではなく、「10%で引くカードを50%で引くようにする」ような低精度のものもあります。積み込みに失敗したなら真っ当に戦って勝てばいい、それでも十分勝率を上げることはできている…ということなのでしょう。
そうした低精度の不正においては、このようなシャッフルの傾向を利用するものもあります。
こうした不正は、精度と引き換えに、怪しまれるアクションを取らずにできるようになっているので、こちらから見抜くことは難しいです。
という情報をもとに不正対策は考えていく必要があります。
相互シャッフルはカットで済ませない、しっかりファローとヒンズーを両方行うことが一番の対策です。カジュアル志向のイベントならともかくとして、競技志向のイベントではしっかり不正対策に取り組み、自衛していきましょう。それが他の公正な参加者を守ることにもつながります。
40枚(デュエマ)
12回目のシャッフルで初期配列に戻ることが確認できます。
案外少ない回数で初期配列に戻るんですね。
ファローシャッフルがスリーブを痛めるというのは(たぶん)勘違い
「ファローシャッフルはスリーブを痛めるから嫌い」ということを仰るプレイヤーもたまにいらっしゃいます。
私の経験上の話ですが、このようなことを仰るプレイヤーのほとんどは、そもそもファローシャッフルのやり方を知らないか、あるいはやり方を勘違いしていることが多いのです。
正しいファローシャッフルの方法を伝授すれば、ほとんどの場合は勘違いが解消されてファローシャッフルを忌避しないようになります。あと「カッコいいシャッフルができるようになった」といって喜んでくれます。
そもそもファローシャッフルは、
①山札を二つの束にわけて両手で持つ
②片方の束を、片方の束の上に持っていき、
③上に持って行った束を重力に任せて落下させ、下の束の隙間に差し込んでいく
という操作です。
この
「重力にまかせて落下させる」というところが重要で、カードに対して直接力を加えて差し込むわけではありません。
重力にまかせて落下させているだけなので、無理な力が加わることはありません。もし失敗したとしても、上の束が下の束に差し込まれず弾かれて、テーブル上にバラバラと散らばるだけで済みます。
正しい手順でやれば、ファローシャッフルでスリーブが避けたり、カードが折れたりということは起こりえないわけです。
ファローシャッフルの正しい手順はYoutubeなどで紹介されていますので、ぜひ動画を見ながら練習してみてください。
カードゲーマー必修科目『ファローシャッフル』についてよく使う3種類を紹介します
動画がいいなと思っていただけたら高評価ボタンを押してください!動画制作のモチベーションになります!そして少しでも面白いなと思っていただけたらぜひ【チャンネル登録】をよろしくお願いします!※デッキリストの送り先はTwitterのDMまでお願いします!リジェのTwitter https://twitter.com/r...
リフルシャッフルがスリーブを痛めるというのは事実。中身のカードも終わる
リフルシャッフルは原則やってはいけません。カードがダメになるからです。スリーブもシワができて使えなくなります。
デュエマやMTGのようなコシのあるカードだったとしても、やるべきではありません。紙にダメージが入って、一気に損耗が進んでしまいます。
リフルシャッフルは要らないカードの束で練習するだけにしておいてください。
シャッフル中に違和感を感じたら、その時点でシャッフルを中断しよう
シャッフル中に違和感を感じたときは、カードに無理な力が加わっていることがあります。
そのまま続けているとスリーブが避けたり、カードが折れたりというトラブルにつながるかもしれません。
「何か変だな」と思ったら、その時点で直ちにシャッフルを中断し、デッキをテーブルに置くようにしましょう。緊急回避的な対応なのですから、綺麗な束の状態で置けなくても構いません。
ハンドシャッフル(シャカパチ)は無駄な行為ではない
ハンドシャッフルというのは、手札をシャカシャカと混ぜる行為です。シャカパチとも言います。
ハンドシャッフルは音が鳴ることばかりが取り沙汰されて、無駄な行為だと思っている人も多いようです。
実際ハンドシャッフルは音が鳴ります。スムーズにやろうと思うと、紙のコシを使っての操作になるので、どうしても音が鳴ってしまうんですよね(パチーンと大きな音を鳴らす人もいますが、あれは必要ないですね)
TCG初心者の方に「それって意味あるんですか?」としばしば聞かれるのですが、その都度丁寧に教えるようにしています。
ハンドシャッフルには戦略的に重要な意味があり、そのことを知っているか/知らないかということがプレイスキルに関わってくるからです。
教えおわった後に
「カードゲームはこんなにも深いものだったか」と感激されることもあって、そんなことがあるたびにこちらも初心を思い出して感じ入ってしまいます。
ハンドシャッフルの意味
仮に対戦相手がまったくハンドシャッフルをしないでプレイするとしましょう。
-
4ターン目、対戦相手がターン開始時に引いたカードをすぐさまプレイした。プレイしたのは《A》というカードだった。この後、対戦相手の手札は残り4枚になっていた。
上記のようなプレイを見て、わたしたちはどのような情報を得ることができるでしょうか。
ターン開始時に引いたカードそのままプレイしたので、引いたカードは手札に残っていません。当然
「対戦相手が持っている残り4枚の手札の内容は、前のターンから持っていた手札と同じである」ということがわかります。
対戦相手がハンドシャッフルをしなかっただけで、まあまあ重要な情報が得られてしまうのです。
ここで仮に、
-
3ターン目、対戦相手が《B》を持っていたならば、当然《B》をプレイするだろう状況だったが、実際にプレイしたのは《C》だった。この後、対戦相手の手札は残り4枚になっていた。
という情報を追加してみます。
すると、まず
「対戦相手は3ターン目までに《B》を引いていなかったのだろう」ということが推察されます。
そして、4ターン目に引いたカードの内容も判明してしまっているので、4ターン目にも依然として《B》を引いていないことがわかります。
ハンドシャッフルをしなければ、ドローの度に対戦相手に情報を与えてしまいます。こういう情報が積み重なっていくと、対戦相手の手札の推測の精度が高まっていき、ゲームの勝敗に関わるほど大きなアドバンテージになってしまいます。
真剣にプレイしたいのであればこまめにハンドシャッフルしたほうが良いでしょう。
ハンドシャッフルすべきタイミング
ハンドシャッフルをすべきタイミングは、何かしら手札に変化があった後のタイミングです。たとえばドローした直後、ルーティングの直後、別のゾーンからカードを手札に加えた直後などがそうでしょう。
対戦相手の視線から、手札のうちのどのカードが重要なカードなのか判断できるプレイヤーもいるので、ランダムハンデスの直前にも混ぜた方がいいです。
ですが、タイミングでハンドシャッフルすべきかと考えながらプレイするのは、微妙に思考力が削がれてしまいます。それで肝心のプレイに集中できなければ元も子もありません。
そういうことも加味すると、
タイミングに関わらず定期的にハンドシャッフルするようにした方が効率的…となってしまうんですよね。
そういうわけで、ゲーム中ずっとハンドシャッフルしているプレイヤーというのが生まれるわけです。アレもまた、ハンドシャッフルに関わる戦略の一環だったりするのですね(そしてそれがすっかり癖づいてしまっているのでしょう)
特にデュエルマスターズは手札の移動が頻繁に発生するので、ハンドシャッフルの必要なタイミングが多いです。だからなおさらゲーム中ずっとハンドシャッフルしておこう…となるようですね。あのゲームのプレイヤーは殊更にハンドシャッフルが多いように感じます。
パイルシャッフルはデッキの無作為化手段として不十分
パイルシャッフルには、デッキ内のカードが決まった形で法則通りに移動させるという性質があります(ただカードをならべているだけなので、そうなるのは当然ですが)
ゆえに、パイルシャッフルをしても山札の配列は無作為にはなりません。あらかじめ配列を仕込んでおいた山札をパイルシャッフルすれば、意図したとおりの配列の山札をつくることができます。いわゆる
「積み込み」という不正行為です。
そうして配列を操作した山札に対してフォールス・シャッフルを行えば、見かけ上はシャッフルしているのにも関わらず中の配列はほとんど変わらないまま、ということができてしまいます。
フォールス・シャッフル
フォールス・シャッフルというのは、一見カードを混ぜているように見えて、実際は配列を変化させていないカード操作のこと。偽のシャッフル。ファローシャッフルを行っても山札トップ付近のカードは大きく移動しないため、これによって初手引きをコントロールする不正行為も存在する。
積み込みの内容とパイル数次第では、対戦相手のカットで積み込みが壊れされないようにすることも可能です(試合前の相互シャッフルはしっかりやりましょう)
こうした問題があることから、パイルシャッフルはシャッフルの手段として適切ではありません。実際、デュエルマスターズやMTGでは、パイルシャッフルはシャッフルの方法として認められていません。
ですが、デュエルマスターズやMTGにおいてパイルシャッフルが完全に禁じられているわけではありません。むしろ試合前にパイルシャッフルを行うプレイヤーは多いです。
…が、あくまでこれは
「山札数のカウント」という名目のもとに行われます。
「山札数のカウント」という名目である関係で、パイルシャッフルはデッキ枚数の約数で分けた方が無難です。40枚の山札を数えるのに、8ではなく、13や7で分けていたら端数がでてしまいます。山札数のカウントをするのにどうしてそんな方法でやるのか、何かカウント以外の意図があるんじゃないか、という疑念が生じてしまいます。
(もっとも、積み込みの手段は多彩であり、山札枚数の公約数だから不正でないというものでもありませんし、公約数じゃないから不正だというものでもありません)
また、「山札のカウントのため」という名目である以上、パイルシャッフルは原則ゲーム開始時のみにしか行えません(MTGではイベント規定により禁止、デュエマでは禁止されていないが後述の理由により非推奨)。ゲーム最中にパイルシャッフルをするのはやめておきましょう。
ゲームの最中、シャッフルのたびにパイルで山札を数えなおすというのは非常に奇妙な行動ですし(カードが盤面上に展開されている状況で、わざわざデッキを並べてパイルシャッフルしている光景を思い浮かべてください)、実際に積み込みを行うプレイヤーはゲームの最中にパイルシャッフルを挟んでくることがあるので、そういう事情もあってますます疑われてしまいます。
カードゲーム世界に馴染むまでは「相手のカードは触らない」を基本にした方がよい
カードゲーム初心者の頃は、カードの価値や扱い方がわかっていないために、トラブルの原因となるような危ないカードの扱い方をしてしまうことがあります。
具体的には、相手のカードを指定する時に爪の先で叩くとか、手札破壊するカードを選択する時に相手の手札からカードを引き抜くとかです。
TCGのカードはトランプのように扱ってはいけません。そういうことすると、カードがへこみますし、折れます。
それで弁償を求められたとして、現実的な価格のカードなら良いのですが、5~6桁円で取引される超プレミアムなカードだった場合は大変です。
いかにも高額そうな絢爛仕様のカードだけが高いわけではありません。全然光ってもいないし、いかにも普通そうな雰囲気のカードが5~6桁円で取引されていることだってあります。
こういうのは特にMTGだとザラにあることです。MTG以外では、デュエルマスターズの旧枠カードもものすごいプレミアムがついています。特別豪華な仕様ではない、普通のぺらっとしたホイル加工のカードが5桁円で取引されるようになっています。
デュエルマスターズは子供向けホビーだったために、公園のベンチや自宅のガレージなど劣悪な環境でプレイされていて、カードの保存状態が非常に悪いのです。あるいは単純にメーカー側の製造方法に問題があって、よい状態で残っていないカードというのもあったりします。そういうわけで、デュエルマスターズ旧枠カードは美品在庫が希少であり、有名旧枠カードの美品の価値が近年急騰しています。希少すぎて通販では在庫が見つからない…なんてことも珍しくありません。
話を戻しますが、TCGのカードの扱い方というものがわかってくるまでは、対戦相手のカードは触れないようにしましょう。トランプやUNOの感覚でカードを触ると、とんでもないことになってしまいます。
カードを指定する時も直接触らずに、「指差し」を基本にしましょう。TCGのカードの扱い方というものがわかってくるまでは…と言いましたが、ベテランプレイヤーでも相手カードを極力触らないようにしている人は多いです。
相互シャッフルの時も、慣れていない間は相手デッキのシャッフルを辞退するのが無難です。
今回の記事のテーマとは関係のないことでしたが、とてもとても大切なことなので、最後に書かせていただきました。
さいごに
書きたかったことは大体かけたので、今回はここまでにします。
この記事が皆さんのトラブル回避の役に立ったなら、長くTCGを続けていくことに貢献できたなら幸いです。
この記事を共有する
広告
関連記事