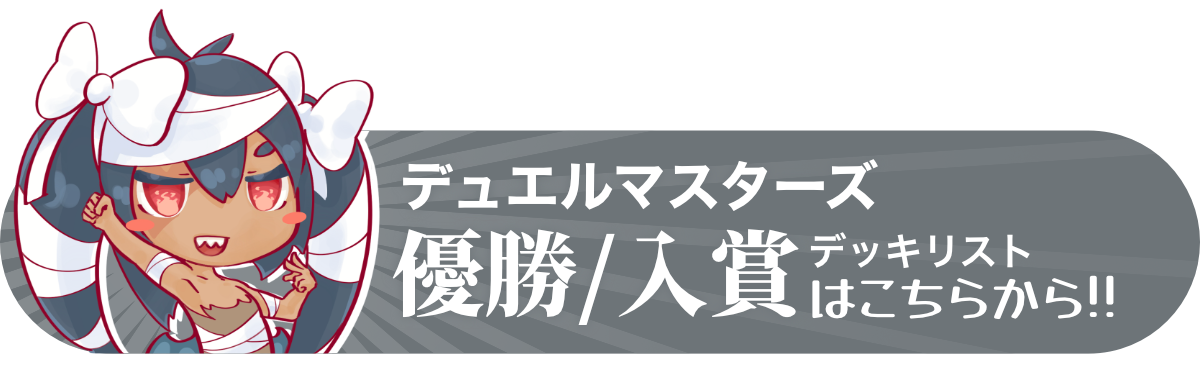【格安モダン/予算 ¥11000】黒単ゾンビ(2022/11/23更新)

こんな内容の記事です
- 予算¥11000で構築できる格安モダンデッキの紹介です!
- 予算は2023/6/28のWisdom Guildトリム平均価格から一の位を切り上げたものを参考価格とし、それを合計して算出しています。
- 即興でコンボを組み立てながら、テクニカルに攻めていくデッキです!
- 現状のメタゲームで十分勝てる仕上がりですがプレイ難度は高めです。モダンらしい難しさとアンフェアさが味わえるデッキになっているので、モダンを遊んでみたかった方におすすめしたい格安モダンデッキになっています。
- 記事公開後にデッキリストを更新しているため、記事の解説とリストとに齟齬が生じている部分があります。
リスト
カード名をタップで詳細ページに飛びます。
記事公開後にデッキリストを更新しているため、記事の解説とリストとに齟齬が生じている部分があります。
メイン
クリーチャー
4 よろめく怪異 ¥ 904 墓所這い ¥ 380
4 屍肉喰らい ¥ 210
4 滅びし者の勇者 ¥ 260
4 アンデッドの占い師 ¥ 70
2 ぬかるみのトリトン ¥ 50
1 忍耐強く企む者、ゴラム ¥ 50
4 戦墓の巨人 ¥ 300
4 首無し騎手 ¥ 220
呪文
4 村の儀式 ¥ 404 骨の破片 ¥ 40
土地
1 見捨てられたぬかるみ、竹沼 ¥ 70020 沼
サイドボード
2 死鳴らし鬼 ¥ 402 エレヒの石 ¥130
4 絶望の力 ¥ 240
2 ダウスィーの虚空歩き ¥ 1030
2 ぬかるみのトリトン ¥ 50
2 完全無視 ¥ 30
1 血の芸術家 ¥ 190
予算
メイン:¥ 7290サイドボード:¥ 3710
合計:¥ 11000
テストプレイ
プロキシ印刷
また、MOXFILEDのプロキシには基本土地が含まれません。
- カラー
- 用紙サイズ:A4
- 1枚当たりのページ数:1
- 余白:デフォルト
- 倍率:既定
うお…!?
異様に安いなこれ…!?
異様に安いなこれ…!?
こんなに安いのに結構勝てるんですよ…!
広告
デッキ・リニューアルのコンセプト
リニューアル前の格安黒単ゾンビデッキ
リニューアル前の黒単ゾンビは、《アンデッドの占い師》や《村の儀式》で対戦相手の除去呪文からカード・アドバンテージを吸い取っていくデッキでした。カード・アドバンテージ
使うことができるカードの枚数。あるいはその枚数の差によって得られる優位性のこと。複雑な概念であり、一律に定義できるものではないが、「場のクリーチャーの枚数と手札の枚数を足した枚数」で考えることが多い。
カード画像はタップで拡大します。
(外側をタップすれば拡大した画像を閉じます)
要するに「今のモダンでチンタラ戦うデッキには芽がないからスピードアップする」ってことだよな。
そうなんですよね。
カードパワーの高いカードを多数採用するならロングゲームにも耐えうるのですが、それができるデッキタイプは限られますし…
カードパワーの高いカードを多数採用するならロングゲームにも耐えうるのですが、それができるデッキタイプは限られますし…
そういうデッキはカード1枚1枚が本当に高いしな…
どうリニューアルしたのか?
《屍肉喰らい》を主役に据えたゲームメイクをできるようにした
《屍肉喰らい》は、味方クリーチャーを生贄に捧げて自身をパワーアップする能力を持ったゾンビ。味方ゾンビ死亡時にゾンビトークンを生成する《首無し騎手》で、除去を浴びてもクロックダウンしないようにした
《首無し騎手》は自身を含む味方ゾンビの死亡時に2/2ゾンビトークンを生成する能力を持っています。|
首無し騎手
クリーチャー - ゾンビ {2}{黒} 首無し騎手かあなたがコントロールしていてこれでもトークンでもないゾンビ1体が死亡するたび、黒の2/2のゾンビ・クリーチャー・トークン1体を生成する。 |
アグレッシブサイドボーディングを取り入れて、苦手対面を勝ちやすくした
《ぬかるみのトリトン》4枚と《戦墓の巨人》3枚をサイドインして、墓地活用のミッドレンジへとアグレッシブサイドボーディングするパッケージを搭載しています。
「続唱サイ」とのマッチアップが「マシに」…か。
もっと有利に立ち回れるようになればよかったのですが…
やっぱり厳しかったです。
やっぱり厳しかったです。
広告
即興でコンボを組み立てていく頭脳派デッキ
「格安黒単ゾンビ」は各々シナジーを持つカードで構築されています。
ハマったときの爆発力がすごいから、モダンでもしっかり勝ちに行けるんですよね…!
「ハマったときの爆発力が…」みたいなデッキが今のモダンで強いのはたしかだな。
高額なパワーカードを使うわけじゃない限り、自分のムーヴを押し付けるデッキを組むのが正解らしい。
高額なパワーカードを使うわけじゃない限り、自分のムーヴを押し付けるデッキを組むのが正解らしい。
MTGに限らず、デッキタイプの多様性が大きいカードゲームはそうなりがちですね。
対策を立てる仮想敵が多すぎると、対策を立てる行為それ自体の意味が希薄になりますから、必然的に強いムーヴの押し付け合いへとメタゲームが傾倒していくんですよね。
対策を立てる仮想敵が多すぎると、対策を立てる行為それ自体の意味が希薄になりますから、必然的に強いムーヴの押し付け合いへとメタゲームが傾倒していくんですよね。
まぁ、それはそれで面白いけどな。
自分のデッキに習熟していけば勝てるわけだから、ある意味「モダンはやりこみ」の時代に戻ったともいえるか。
自分のデッキに習熟していけば勝てるわけだから、ある意味「モダンはやりこみ」の時代に戻ったともいえるか。
好きなデッキを使い込んで勝てるのがこのフォーマットの魅力でしたからね。
基本のコンボ:屍肉喰らい+墓所這い
《屍肉喰らい》は前述の通り、味方一体を生贄にパワーアップするゾンビ。 一方、《墓所這い》は何度でも墓地から召喚できるゾンビ。
基本のコンボに噛ませたいカードたち
滅びし者の勇者
見てください、この哀愁漂う戦士の横顔を。
カッコいい…カッコよすぎます…!
カッコいい…カッコよすぎます…!
お、おう…
《屍肉喰らい》や《墓所這い》がなくても育つから、安定して活躍してくれそうだな。
《屍肉喰らい》や《墓所這い》がなくても育つから、安定して活躍してくれそうだな。
アンデッドの占い師
十分な枚数の手札が確保できれば《アンデッドの占い師》を生贄に捧げてライフロスを止める必要があります。
油断してるとライフが空になってしまいます。
ライフが少なくなりすぎると、チャンプブロックすらマトモにできなくなるわけか…
ですね。
どれだけカードを引ければ十分なのか、どれだけライフが必要なのか、常に意識しながら使う必要があります。
どれだけカードを引ければ十分なのか、どれだけライフが必要なのか、常に意識しながら使う必要があります。
うーん…なるほど、見た目以上扱いが難しそうだ…
首無し騎手
ブロックされなかった《屍肉喰らい》や《滅びし者の勇者》をこのテクニックで強化して押し切る…という展開は珍しくないんですよね。
これが使いこなせるようになると、かなり勝てるようになると思います。
これが使いこなせるようになると、かなり勝てるようになると思います。
こういうテクニックは自分も忘れがちだけど、相手にとってはもっと意識外なものだからな。
そもそもゾンビはそんなにメジャーなデッキタイプじゃないし。
そもそもゾンビはそんなにメジャーなデッキタイプじゃないし。
そうなんですよね。
だから熟練の相手であっても、盤面を見落として誤ったブロック指定をしてしまうことは珍しくありません。 その一瞬の隙を突いて一気にパワーアップして決着させちゃいましょう…!
だから熟練の相手であっても、盤面を見落として誤ったブロック指定をしてしまうことは珍しくありません。 その一瞬の隙を突いて一気にパワーアップして決着させちゃいましょう…!
《屍肉喰らい》と《墓所這い》が揃わなくても大丈夫
《屍肉喰らい》と《墓所這い》のセットが「基本のコンボ」としましたが、別にそろわなければ勝てないというわけではありません。
小粒を並べてロードで強化して殴るだけ勝てちゃったりするのが部族デッキなんだよな…
相手が除去呪文を握ってなければ、並べて殴るだけで勝てちゃったりするんですよね。
広告
なぜこんなに安いのか?
そもそも部族デッキというものが安い
ここまで予算が安価になったのは、数少ない高額カードだった《墓所這い》が『ダブルマスターズ2022』にて再録され、シングル価格が大幅に下がったから。
他のデッキでは使用されないからパーツが安くなるというのは、部族デッキあるあるですよね。
特殊地形が少ないのは…
もっぱら《血染めの月》対策です。そのため、本リストは20枚中18枚を沼にし《血染めの月》へのガードを固くしています。
最近の赤系フェアデッキはメインから《血染めの月》を入れてあるから、単色デッキであっても《血染めの月》は要警戒なんだよな。
そうなんですよね。
今のびのびと特殊地形が使えているのは赤単くらいのものではないでしょうか…
今のびのびと特殊地形が使えているのは赤単くらいのものではないでしょうか…
赤単は特殊地形が山になってもあんまり痛くないからな…
メインから《血染めの月》が使われていくうちに、「対面が単色デッキであろうと特殊地形の採用が多ければ刺さる」という通念が浸透してしまったのも大きい。
メインから《血染めの月》が使われていくうちに、「対面が単色デッキであろうと特殊地形の採用が多ければ刺さる」という通念が浸透してしまったのも大きい。
それもあります…
分かってるプレイヤーは単色相手にも《血染めの月》を使ってくるようになりましたよね。
分かってるプレイヤーは単色相手にも《血染めの月》を使ってくるようになりましたよね。
採用カード解説
屍肉喰らい
コンバット・トリックもできて、追放対策もできて、シナジーも豊富で、実質的に味方が除去されるたびに強化される1マナクリーチャーか…
長所を枚挙すれば本当に強いクリーチャーだと分かるな…
長所を枚挙すれば本当に強いクリーチャーだと分かるな…
パッと見た感じは地味な性能なんですけど、使えば使うほど強さが分かってくるカードなんですよね…
巣のシャンブラー
でてきたリスくんも《屍肉喰らい》のエサにすれば+2/+2です…!
リスくんまで…
よろめく怪異
|
クリーチャー - ゾンビ {黒} 1/1 よろめく怪異が死亡したとき、以下から1つを選ぶ。 • 悪臭を我慢する — 対戦相手がコントロールしているクリーチャー1体を対象とする。ターン終了時まで、それは-1/-1の修整を受ける。 • 死体を調べる — 宝物・トークン1つを生成する。(それは、「Tap, このアーティファクトを生け贄に捧げる:好きな色1色のマナ1点を加える。」を持つアーティファクトである。) |
スタンダードでも大いに活躍したので、覚えている方も少なくないかと思います。
|
敏捷なこそ泥、ラガバン
伝説のクリーチャー - 猿・海賊 {赤} 2/1 敏捷なこそ泥、ラガバンがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたび、宝物・トークン1つを生成し、そのプレイヤーのライブラリーの一番上のカードを追放する。ターン終了時まで、あなたはそのカードを唱えてもよい。 疾駆{1}{赤}(あなたはこの呪文を、これの疾駆コストで唱えてもよい。そうしたなら、これは速攻を得て、次の終了ステップの開始時に、これを戦場からオーナーの手札に戻す。) |
生贄ありきではありますが、1枚で二役担えるのは優秀です。
実質モード呪文みたいなものだからな。
有用な場面が多いカードは、デッキの平均的なパフォーマンスを高めてくれる。
有用な場面が多いカードは、デッキの平均的なパフォーマンスを高めてくれる。
村の儀式
サイドボード解説
アグレッシブ・サイドボーディングでマッチアップを改善する
「バーン」「続唱サイ」「ドメイン・ズー」などの対面では、アグレッシッブ・サイドボーディングでデッキを墓地活用型のミッドレンジへと変形させ、マッチアップの改善を図ります。 その際入れ替えるカードは以下の通り。IN
4 ぬかるみのトリトン3 戦墓の巨人
OUT
4 巣のシャンブラー2 呪われた者の王
1 死の男爵

腐敗した再会
|
インスタント {黒}
墓地にあるカード最大1枚を対象とする。それを追放する。腐乱を持つ黒の2/2のゾンビ・クリーチャー・トークン1体を生成する。(それではブロックできない。それが攻撃したとき、戦闘終了時に、それを生け贄に捧げる。) フラッシュバック{1}{黒}(あなたはあなたの墓地にあるこのカードをフラッシュバック・コストで唱えてもよい。その後、これを追放する。) |
リアニメイトデッキや《頑強》を搭載した「独創力」には有効ですが、墓地肥やしのスピードが圧倒的な「ブルーリビングエンド」には敵いません。
腐乱
「腐乱」を持つクリーチャーは、ブロックすることができず、攻撃に参加した戦闘の終了時生け贄に捧げられる。絶望の力
|
インスタント {1}{黒}{黒}
あなたのターンでないなら、あなたはこの呪文のマナ・コストを支払うのではなく、あなたの手札から黒のカード1枚を追放してもよい。 このターンに戦場に出たクリーチャーをすべて破壊する。 |
|
ヴェクの聖別者
クリーチャー - 人間・クレリック {1}{白} プロテクション(黒)、プロテクション(赤) ヴェクの聖別者が戦場に出たとき、すべての墓地から黒や赤であるすべてのカードを追放する。 黒や赤の、パーマネントや呪文や戦場にないカードが墓地に置かれるなら、代わりにそれを追放する。 |
そもそもピッチスペルの除去呪文というだけで優秀なんだよな。
そうなんですよね…!
3マナ払って唱えるにはちょっと微妙な性能ですが、ハードキャストすることはほぼほぼないので問題ありません。
3マナ払って唱えるにはちょっと微妙な性能ですが、ハードキャストすることはほぼほぼないので問題ありません。
ドロー手段も多いから、ピッチコストに困ることもそうないだろうしな。
残忍な騎士

|
クリーチャー - ゾンビ・騎士 {1}{黒}{黒} 2/3 絆魂 残忍な騎士が死亡したとき、これをオーナーのライブラリーの一番下に置く。 迅速な終わり インスタント - 出来事 {1}{黒}{黒} クリーチャー1体かプレインズウォーカー1体を対象とし、それを破壊する。あなたは2点のライフを失う。(その後、このカードを追放する。あなたは後で追放領域からこのクリーチャーを唱えてもよい。) |
完全無視
広告
デッキをさらに強化するには?
現状、強化の余地はほぼありません。
良くも悪くも完成されているリストなのです。
カスタマイズして楽しみたいというプレイヤーにはツラいところかもな…
「赤単果敢」の方は好きなカードでカスタムする自由度があるのですが、如何せんこちらはゾンビシナジーと生贄のシナジーとで固めているのでカスタマイズ性が低いんですよね…
「安くて強いデッキ」はカードじゃなくてデッキが強い構築にせざるを得ないからな。
ちょっと弄れば弱くなるような繊細なものになってしまうのも当然か。
ちょっと弄れば弱くなるような繊細なものになってしまうのも当然か。
広告
まとめ
というわけで黒単ゾンビの紹介でした…!
うーん、今回も長かったな…
記事もだが、リストの調整期間が長かった。
記事もだが、リストの調整期間が長かった。
今の混沌極まるモダンで勝てるようになるまで、かなり紆余曲折ありましたからね…
ロード抜いたりロード入れたりな…
《朽ちゆくゴブリン》とか《疫病吹き》も試しましたね…弱かった…
いやまぁ…弱いカードじゃないんだが、メタゲームにもデッキにもハマってなかった感じだな。
細かく説明しましたが、記事の内容は頭の片隅に入れておく程度で大丈夫ですよ。
まあ、全部覚えてなくてもデッキは回せるしな。
実戦で上達していけばいい。
実戦で上達していけばいい。
ですね!
実際にデッキを組んだ場合にはこの記事をブックマークしておいて、ときどき見返すといいかもです。
実際にデッキを組んだ場合にはこの記事をブックマークしておいて、ときどき見返すといいかもです。
「あそこであのテクニックを使えばよかったのか」みたいな気づきがあるかもな。
今回もおつきあいくださりありがとうございました。
またの記事でお会いしましょう…!
またの記事でお会いしましょう…!
それじゃあまたな…!