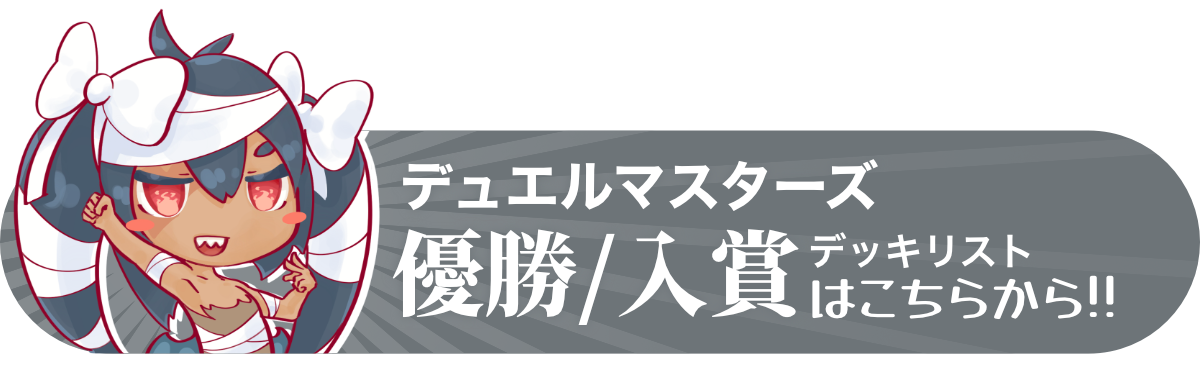本記事は「自分がマスター帯までのラダー中に考えていたこと」を文章化してみたものです。
(ラダー開始はアプリは配信開始日の2025/6/17、マスター到達は2025/7/10、本記事は同期間中のプレイをもとに執筆したものになります)
あくまで、自分が当時考えていたことを詞にしてみたものでしかなく、情報としての確度に微妙なところがありますが、そこはあらかじめご了承ください。
本記事は「『負け当番』というものが本当にあるのか」ということをテーマにしています。あまりこの手の話題には触れたくなかったのですが、人が触れたがらない話題だからこそ他人がどう考えているのか切実に知りたい人もいるだろうと思い、思い切って書きました。
今現在マスターを目指してラダーされている方にとって、この記事が何かしらの助けになったなら幸い至極です。あるいは単純に道楽でTCG記事を漁っている方に楽しんでいただけたなら、それも幸いでございます。
「負け当番」とは
負け当番とは
「プレイヤーの勝敗率を操作するアルゴリズム(ダークパターン)が存在するのではないか」という説。
一見突拍子もない説ですが、実はこのような考えは世界中に広く存在します。
諸外国で進むガチャ(ルートボックス)規制には、ギャンブル性以外にもダークパターンへの危惧があったりします。
#StopKillingGames運動に対して企業が反発するのは、ダークパターンの露見を恐れているからではないかという意見がRedditに投稿され、話題を集めました。
https://www.reddit.com/r/gaming/comments/1ltpu3k/the_real_reason_big_corporate_is_afraid_of_the/?utm_source=embedv2&utm_medium=post_embed&utm_content=post_title&embed_host_url=https://www.gamespark.jp/article/2025/07/08/154806.html
そこでのディスカッションを見るに、オンラインゲームのダークパターンはほとんど公然の事実とされており、少し衝撃を受けました。
日本ではあまりこういう話題に言及する人は少ないですからね…
もっとも、ルートボックスのダークパターンが露見したケースは少なからず存在するので、そのように考える方が自然なのかもしれませんが。
そもそもシャドバが事故しやすいゲームである可能性
まあ、それはそうとして、
シャドウバースに「負け当番」など本当にあるのでしょうか。
それを考えるにあたって、まずは
「そもそもシャドウバース自体が手札事故を発生させやすいゲームシステムである」可能性についても検討せねばならないでしょう。
実は「負け当番」などなく、単にシャドウバースが滅茶苦茶手札事故が発生しやすい運ゲーだった…ということもあり得るからです。
手札事故
手札の極端な偏りによって、非常に苦しいゲーム展開になってしまうことを表すTCGスラング。単に「事故」とも。
デュエル・マスターズの例
さて、多くのTCGには、何かしら手札事故の影響を軽減する工夫がなされています。シャドウバースに実装されている「マリガン」もそのひとつです。
デュエル・マスターズとマナ
日本で人気のある
「デュエル・マスターズ」では、手札をカードを使うためのエネルギー(マナ)にするマナシステムが採用されています。
デュエルマスターズの「マナ」
デュエルマスターズでは、各ターンに1枚、手札のカードをマナとしてマナゾーンに置くことができる。マナゾーンにあるカードは、1枚につき、1点のコストの支払いに使用することができる。使用されたマナはタップ(横向き状態)になり、そのターン中使用できなくなるが、次の自身のターンの開始時にアンタップ(縦向き状態)になり、再度使用可能になる。
手札の不要なカードをマナとして活用していくため、初手に不要なカードをたくさん引いてしまったとしても、シャドウバースほど深刻な影響を受けることはありません。いらないカードはマナにしてしまえばいいからです。
毎ターンマナに1枚、プレイするカードで1枚、という形で各ターン2枚ずつカードを消費していくのもポイント。
手札が減るのを抑えるには、3ターン目に3マナのカードを、4ターン目に4マナのカードをプレイして、手札の消費を効率化するのが大切です。例えば、4ターン目に2マナのカードを2枚プレイするなどしてしまうと、1枚多く手札を消費してしまいます。
ゆえに、先のターンを見越しながら3マナ、4マナ、5マナ…のカードを手札に残していかねばなりません。
裏を返せば、これはマナシステムが「各ターンにプレイしたいカードが手札に残っていくシステム」である、ということでもあります。
漸減する手札を使い切るためのマナカーブ
このマナシステムによって、なだらかなマナカーブを描くデッキ構築に、大きな意義が生じています。
マナカーブ
デッキ内のカードをコストごとにまとめ、その枚数をグラフにしたもの。
序盤は引いたカードの枚数が少ないので、当然、欲しいカードを引いている可能性が低くなります。たとえば先手2ターン目の場合、初手5枚とターン開始時ドロー1枚で合計6枚しか引いていません。
デュエマにおいて4枚採用のカードを先手2ターン目に引く確率は49%、8枚採用にすれば76%になります。
だから序盤にプレイしたいカードはたくさんデッキに入れて、引く確率を上げておく必要があるわけですね。
逆に、中~終盤にプレイしたいカードは、それまでにたくさんカードを引いているから、引く確率が高い。4枚採用のカードを先手8ターン目に引く確率は80%もあります。だから、7マナや8マナのカードは少なくしてもかまわないわけです。
こうしたマナカーブに沿ったデッキ構築ができるのは、いらないカードをマナにするマナシステムがあるからです。マナシステムの恩恵を受け、マナカーブに沿ってデッキを組むから、事故が生じずらい。そういう構造があるわけですね。
(もっとも、デュエマがそのようなゲーム性であったのは、勝舞編か、遅くとも勝太編前半までで、それ以降のデュエマに必ずしも当てはまるものではありません。ただし、近年のデュエマであってもシールド戦ではこうしたゲームの基本構造への理解が問われるシーンが多々あります。)
シャドウバースデッキ確認画面のこの表示がマナカーブ
これだけでは説明がつかない
ですが、これだけではシャドウバースにおいて事故が発生しやすい理由を説明できていません。
マナシステムはマナカーブに沿った構築に意義を与えていますが、
マナシステムがなければマナ・カーブに沿った構築ができないというわけではないからです。
マナシステムの有無にかかわらず、マナカーブに沿った構築には一定の意義があるので、シャドウバースにおいてマナ・カーブが崩れたデッキが多い理由の説明としてはイマイチ弱いのです。
シャドウバースを運ゲー化させるもの
高コスト採用枚数を多くするしかないバランス
そもそも、シャドウバースにおいてマナ・カーブに沿ったデッキ構築ができない理由は、コストとカードパワーの相関関係にあります。
コストとカードパワーとの間に指数関数的な関係があり、高コストカードはすさまじいカードパワーを有しています。低コストのカードを複数プレイするより、高コストカード1枚をプレイするほうが俄然強い調整になっているので、
必然的に高コストカードを厚く採用する構築にせざるをえません。
フォロワーの除去手段が多い調整になっているので、高コストの疾走持ちフィニッシャーなしで決着を狙うことが難しいというのもあります。
ロイヤルやネメシスのようなミッドレンジ型のデッキであっても、7コスト以上のカードの採用枚数が多い尻上がり型のマナ・カーブになっているのは、高コストカードの強さに由来することでしょう。
単純にカードプールが狭い
それに加えて、カードプールの狭さも無視できない事情です。クラスによっては特定マナコスト帯に実用的なカードが存在せず、それでマナカーブがガタガタになっていたりもします。
カードを「腐りやすく」する進化権システム
加えて、進化権システムも事故の発生に関わっていると思われます。
極端な例として《改境の天宮・アルエット》があります。
|
|
改境の天宮・アルエット
ネメシス・フォロワー {5} 2/4
【ファンファーレ】『フューチャー・コア』1枚と『パスト・コア』1枚を自分の手札に加える。
【進化時】自分の手札のコスト5以下のアーティファクト・フォロワー1枚を選ぶ。それのコピー1枚を自分の場に出す。
|
このカードを4~5ターン目(進化解禁ターン)にプレイするのが強力であるのは言うまでもありません。超進化解禁の6~7ターン目以降は、超進化時誘発を持つカードや、相手の超進化に対応できるカードをプレイしたいので、アルエットをプレイするタイミングがあまりない。終盤戦では進化権が残っていないことも。だから、一度タイミングを逃すと最後までプレイするタイミングを見いだせないまま…ということになりがちです。
このアルエットのように、進化権の関係でプレイできるターンが実質的に限定されているカードがいくつかあって、それらは最適なタイミング(ターン)で引かなくてはいけない。それがシャドウバースの引きの重要度大きくしている面もあるでしょう。
「負け当番」は存在しないのか?
まあ、そういうわけで、そもそもシャドバは事故しやすいゲームなのであり、「負け当番」などというのはアンラッキーなプレイヤーの妄言なのである…
…と断言することもできないでしょう。
こういうのは、いわゆる「悪魔の証明」というもので、「何かが存在しないこと」を証明することはできません。ゆえに、無いと断言することもできない。
もちろん、無いことを証明できないから「負け当番が存在する」とするつもりはありません。そんなのは暴論です。あくまで「存在しないとは断言できない」というだけのことです。
その上で、実際に不可解な事象に多く遭遇したのなら、何か「確率を偏らせる要素」が存在することを検討してもよいのではないでしょうか。実際、事実がどうなのかということは別として、です。
極端な事象の発生
ラダー中に遭遇した事象とその発生確率
実際のところ、極端な手札事故が生じるゲームが10回以上連続するなどの事象はこのゲームでは珍しくなく、私もラダーの最中に苦しめられました。
しかしながら、それら事象の発生確率を求めてみると、それは実体験に反して極めて低いものだったのです。
たとえば「10ゲーム連続で5ターン目までに特定カード(改境の天宮・アルエット)を引かない」という事象が毎日のように発生しましたが、これが発生する確率はわずか0.03 %(これはマリガンを考慮しない数値であり、毎ゲームフルマリガンで引きにいく場合は0.0005%)しかありません。
また、「5ゲーム連続で3ターン目までに特定カード(ブーストエクステンド・ララミア)を2枚引く」という事象も頻発しましたが、こうなる確率は0.000002%程度。
同じカードを引いてくるルビィ
プレイヤー間で広く知られている事象としては「ルビィの挙動が顕著に偏っている」というのもあり、同じカードを引き直す可能性が極端に高くなっています(体感では40%ほどでした)
|
|
グリードケルブ・ルビィ
ニュートラル・フォロワー {2} 2/2
【ファンファーレ】自分の手札1枚を選ぶ。それをデッキに戻す。自分のデッキから1枚を引く。
|
SNS上で「ルビィ 確率」などのワードで検索すると、同様の投稿が多数ヒットします。
「そういう可能性」を考慮して攻略する
そしてオカルトへ
ここからの話は、自分の想像交じりのことで、確実な情報ではないのでご注意ください。あくまで、こういうことを考えながら攻略を進めた…というだけの話です。
先に述べたような事象を繰り返し経験したこともあって、自分はA帯に突入したあたりから
「ドローが完全ランダムではない可能性」を考慮してデッキリストの調整を行うよう方針を改めました。
先人の考察より
そこでとりあえず、「負け当番」というものに関しての情報がないか、あれこれと情報収集をしてみることにしました。
その過程で知ったことなのですが、旧作シャドウバース時代からシャドウバースの内部処理に関して様々な考察がなされていたようなのです。特に有名な考察として、
「原則としてシャドウバースの山札には順列が存在せず、ドローの都度アルゴリズムに従って引くカードを抽選している」というものがあったようです。
これはちょっと信憑性があるな…と思いました。今作にも当てはまるかもしれない。
シャドウバース運営開発サイドは、各ゲームのログを収集しており、「〇ターン目にカード《✕✕✕✕✕》をプレイしたこと」と勝率との相関のデータなども当然有しているハズです。であるとするならば、各ターンにプレイヤーが引きたくないカード、引きたくないカードを統計的に割り出すこともできるでしょう。
仮にプレイヤーの「運勢値」というものが設定されていたとして、その運勢値の多寡に従って良い/悪い引きをさせることもおおよそ可能であるということになります。
仮に上記が正しいとするならば、諸々の事象が無理なく説明ができるんですよね。ルビィの異常な挙動に対しても、プレイヤーがルビィによって山札へ返すのはその時点で一番〈いらないカード〉であるのは必定であり、運勢値が最低なプレイヤーが山札から統計的に一番〈いらないカード〉を引かされるとして、戻したカードと引いたカードが一致する確率は大きくなることはあるでしょう。
繰り返しになりますが、ここまでの話はあくまで自分の想像でしかありません。ゆえに、確証など何もありません。妄想と仮定の産物でしかないものなので、あまり真には受けないでください。
とにかく、
「自分はそういうこともあるかもしれない」と考えたうえで攻略を練りました…という話ですので、ご注意ください。
オカルトな評価軸
話を戻しますが、そのようなアルゴリズムが実在すると一度仮定してしまうと、カード採用の基準に、通常のTCGとは別な評価軸が発生してしまいます。つまり、
「アルゴリズムの影響を受けにくいカードであるか」という軸です。
具体的には、「特定のターンや特定の状況下でのみ強いカードはアルゴリズムに影響を受けやすく、複数のターンで広く活躍できるカードはアルゴリズムに対して耐性を持つ」と考えました。
前者は《ブーストエクステンド・ララミア》や《改境の再動》です。思い切って全部抜きました。
|
|
ブーストエクステンド・ララミア
ネメシス・フォロワー {8} 2/2
【ファンファーレ】自分の手札のコスト5以下のアーティファクト・フォロワー3枚を選ぶ。それのコピー1枚を自分の場に出す。
【超進化時】自分の場のアーティファクト・フォロワーすべては+1/+1する。
|
後者は《ミリタリードッグ》のようなエンハンス能力を持つフォロワーです。序盤でも中盤以降でも活躍できるため、〈いらないターン〉に〈いらないカード〉としてドローさせられるリスクが小さいかもしれない…と考えました。
|
|
ミリタリードッグ
ロイヤル・フォロワー {3} 4/2
【エンハンス_6】『ミリタリードッグ』2枚を自分の場に出す。
【突進】
|
《新たなる少女・エース》のキャントリップも、中盤以降は疑似的なエンハンスとして見ることができるので、活躍できるターンが広いカードになっています。
(エースからnコストのカードを引いて、それをすぐにプレイするなら、エースは3+nコストのカードだったとみなせます)
|
|
新たなる少女・エース
ネメシス・フォロワー {3} 3/3
【ファンファーレ】自分のデッキから1枚を引く。
【進化時】自分は『クレスト:新たなる少女・エース』を持つ。
(クレスト:【カウントダウン_3】
自分のターン終了時、自分の手札の枚数が5以下なら、自分のデッキから1枚を引く。6以上なら、自分のリーダーを1回復。)
|
プレイ後即座にアーティファクトを「融合」できる《異次元からの銃撃》も疑似的なエンハンスを持つカードであり、《アタック・アーティファクト》を融合してプレイすれば7コストの二面除去として運用することも可能です。手札に残したコアも使ってデストロイ・アーティファクトを融合すれば9コストのモード呪文にもなります(実際はこういう運用が多かったと記憶しています)
|
|
異次元からの銃撃
ネメシス・スペル {4}
相手の場のフォロワー1枚を選ぶ。それを破壊。『フューチャー・コア』1枚と『パスト・コア』1枚を自分の手札に加える。
|
すると、このカードは4,7,9コストでプレイできる疑似エンハンススペルということになり、4ターン目以降から終盤までの様々な局面で活躍できるカードとみなせます。実際そういうカードだったわけですが。
エンハンス、疑似エンハンス以外では《フィルドア》がアルゴリズム耐性のあるカードだと考えました。
|
|
ミリタリードッグ
ロイヤル・フォロワー {3} 4/2
【エンハンス_6】『ミリタリードッグ』2枚を自分の場に出す。
【突進】
|
序盤にはただの熊(2/2/2スタッツ)として有用であり、進化時の確定除去は大型フォロワーが出てくる中〜終盤戦においても相変わらず有用な能力です。ロイヤルにおいては、10ターン目に《ケンタウロスの騎士》と一緒に出して、相手守護を排除しながら疾走7打点をねじ込む運用も可能です。ゆえに、序盤から終盤にかけて広いレンジで活躍できる。〈いらないカード〉になってしまう局面が少ない。
こういうカードを厚く採用すれば、〈いらないカード〉として引かされるカードの枚数が少なくなり、ある程度アルゴリズムを御することができるかもしれない…
仮定に基づいてデッキを組む
そうした試行錯誤の末にできあがったのが下記二種のデッキリストです。AA帯のラダーとマスター昇格戦で使用しました。
アーティファクトネメシス | Deck Portal | Shadowverse: Worlds Beyond(シャドウバース ワールズビヨンド | シャドバWB)公式サイト | Cygames
次世代スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond (シャドウバース ワールズビヨンド | シャドバWB ) 』の公式サイトです。App Store/Google Play/Steam/Epic Games Storeにて好評配信中!
ロイヤル | Deck Portal | Shadowverse: Worlds Beyond(シャドウバース ワールズビヨンド | シャドバWB)公式サイト | Cygames
次世代スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond (シャドウバース ワールズビヨンド | シャドバWB ) 』の公式サイトです。App Store/Google Play/Steam/Epic Games Storeにて好評配信中!
正直、自分でも陰謀論くさいな、馬鹿らしいな、と思いながら練ったデッキリストでしたが、これらを使うようになってから有意に事故率が改善されました。
とはいえ、私個人の体験にすぎないものを以て「現行シャドウバースの仕様がどうなっているのか」ということを断じることは当然できませんし、するつもりもありません。そもそもレンジの広いカードを大量搭載したデッキは、通常のTCGにおいても事故しづらいですからね…
無条件に否定してしまうのは勿体ない
ただ、確率に関して不思議な事象に遭遇してしまった手前、そして自分なりに対策して上手くいってしまった手前、「内部処理に関して想像力を働かせながらプレイするのはおかしい」とも言えないんですよね。
それに、そういう可能性を最初から無条件に排除してしまうのは、ゲームを攻略するという行為において「勿体ない」のではないか、とも思います。
それは紙媒体のTCGにおいても同じことです。「このカードは絶対弱いと思うから使わない」とか「このブラフは意味がないと思うからやらない」とか。やってみなければ効率的に成長する機会を得られないわけですし、やってみたら劇的に効果が出るかもしれない。そういう機会を最初から手放すと、遠回りになってしまいます。
もっとも、「負け当番」のことと、紙のTCGのこととは微妙に性質の異なるものですから、一概に比較できるものではないのですが。
紙のTCGでのトライエラーは現実での出来事であり、どのような結果であっても現実のことと受け止めることができますが、DTCGのアルゴリズムはブラックボックス内での出来事であり、最後まで真偽がわからないんですよね。
それに、「アルゴリズムありきでDTCGを遊ぶなんて楽しいとは思えない」などと言われてしまうと、答えに窮してしまいます。あまりにもメタ的で、シラけるやり方だなと自分でも思っています。
最後に
長々とこういう文章を書きましたが、自分はシャドウバースに対してネガティブな感情は抱いていません。
相当好きじゃなければ、マスターまでやりこんで、ここまでの文量になるほどあれこれ真剣にデッキや攻略を練ったりはしませんからね…
それに、仮にドローの確率を操作するアルゴリズムがあったとして、それが全面的に悪いことだとも思いません。
シャドウバースにおける運要素はドローの部分しかなく、それ以外の部分は完全に実力で決定されています。それゆえに、シャドウバースは実力介入が大きい「難しいゲーム」に仕上がっています。
実力主義のゲームではプレイヤーの淘汰が急速に進んでしまう傾向があります。引き運の強さで気持ちよく連勝できる場面、ジャイアントキリングできる場面というのをつくってやらないと、プレイ人口を維持することはできないでしょう。
(シャドウバースにおいてそうしたアルゴリズムが存在すると確定したわけでもないんですけどね…)
この記事を共有する
広告
関連記事