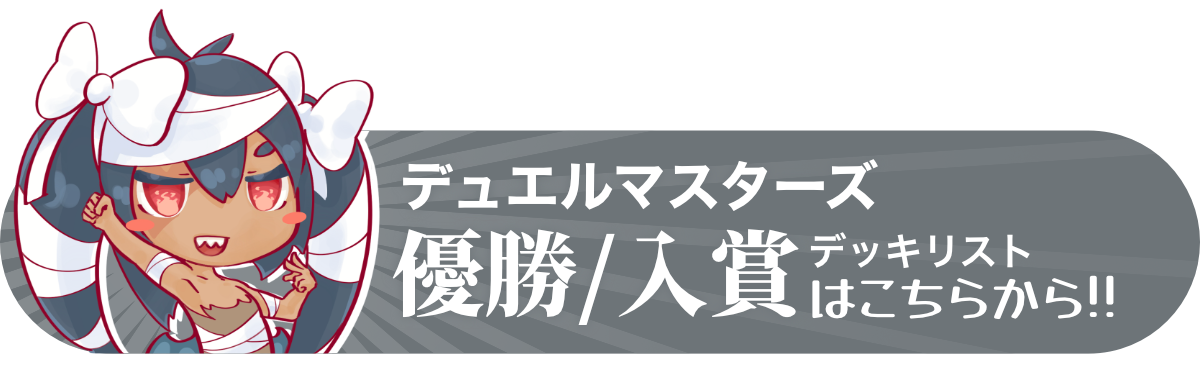この頃、近しいゲーマーたちから
「今度FFとコラボするMTGについて教えてほしい」と度々聞かれるのですが、その都度うまく答えられなくて悩ましく感じています。
というのも、ここ数年のMTGは本当に複雑で、現役プレイヤーたちですらイマイチよくわからなくなっている程だからです。(公式サイトの
https://mtg-jp.com/reading/translated/0038649/を見てみてください。情報量に驚くと思います。)
そういうこともあって、初心者に説明すべきことをあらかじめテキストにまとめておいた方がいいんじゃないかと考え、久しぶりに記事を書いています。身内のプレイヤーらに伝えた内容をそのまま記事に起こしている関係上、無遠慮な書きぶりのところもありますが、ヘンに遠慮があるよりは良いということでご容赦いただければ幸いです。
今回の記事では
「フォーマット」について説明します。
「フォーマット」はMTGを遊ぶ上で絶対に知っておくべきものです。ゲームのルールよりも先に知っておくべきものだといっても過言ではないでしょう。
それくらい大切なものなのですが、これがまたややこしくて、教えるのにいつも苦労してしまいます。
フォーマットとは
「フォーマット」というのは、平たく言えばカードの階級分けです。ミドル級のカードもあれば、ヘビー級のカードもあるというわけです。
実際には、MTGのフォーマットは「ミドル」「ヘビー」という区分ではなく、「スタンダード」「パイオニア」「モダン」「レガシー」「ヴィンテージ」という区分になっています。
もちろん、カード1枚1枚の重さでフォーマットが区分される…なんてことはありません。カードの発売時期によって区別されます。
古いカードであるほど重量級の扱いになり、使用できるフォーマットが少なくなります。
- スタンダード:直近3年間の通常セットのカード
- パイオニア:『ラヴニカへの回帰』(2012年)以降の通常セットのカード
- モダン:『基本セット第8版』(2003年発売)以降の通常セットのカード+α
- レガシー:すべてのカード
- ヴィンテージ:すべてのカード(レガシーよりも使用禁止に指定されたカードが少ない)
※上の表はざっくりとした区分であり、実際はいくつも例外があります。
最も古いMTGのパックである
『アルファ版』に収録されていたカードは、「レガシー」と「ヴィンテージ」でしか使用することができません。
その逆に、『マジック:ザ・ギャザリングーFINAL FANTASY』の通常セットで登場するカードは、スタンダードからヴィンテージまですべてのフォーマットで使用可能になります。
通常セット
公式サイトのフォーマット解説ページにて用いられている言葉だが、具体的に何を指示しているのか定かではない。現状から考えるに「パックやボックスなどの製品から入手でき、スタンダードで一定期間使用可能なものとしてつくられたカードのグループ」と解釈するのが適当であり、本記事ではそのような意味の言葉として用いる。
また、古いカードであっても、新しい通常セットで再録されれば、その通常セットが使用できるすべてのフォーマットで使用可能になります。
再録
過去の製品に収録されていたカードが、新しい別の商品に再度収録されること。再収録。
たとえば《稲妻》は『アルファ版』のカードですが、『基本セット2010』で再録されたので「モダン」でも使用可能という扱いです。
|
|
稲妻
インスタント {赤}
1つを対象とする。稲妻はそれに3点のダメージを与える。
|
例外その1:統率者戦
これまで紹介してきたフォーマット以外にも、フォーマットは存在します。
そのひとつが「統率者戦」です。「コマンダー」「EDH」とも呼ばれていますが、これらの呼称も一般的に使用されているので、あわせて覚えておく必要があります。
「統率者戦」は多人数でプレイするフォーマットであり、構築ルールも独特です。
- 100枚でデッキを構築する
- 各カード1枚ずつのみ使用可能(基本土地は複数枚使用可能)
- 伝説のクリーチャーカードを1枚、デッキのリーダーである「統率者」として指定する
- 選んだ統率者が含む固有色のカードのみでデッキを構築する
たとえば、《迷える黒魔道士、ビビ》を統率者に指定したならば、《炎魔法》をデッキに入れることができます。《炎魔法》の
固有色である赤は、青と赤が固有色である《迷える黒魔導士、ビビ》に含まれているからです。
同様の理由で、青と赤が固有色である《過激な淑女、シャントット》も、《迷える魔導士、ビビ》が統率者であるデッキに入れることができます。
|
|
過激な淑女、シャントット
伝説のクリーチャー ー ドワーフ・ウィザード {1}{青}{赤}
0/4
あなたがクリーチャーではない呪文1つを唱えるたび、ターン終了時まで、これは+Ⅹ/+0の修正を受ける。Ⅹは、その呪文を唱えるのに支払われたマナの点数に等しい。Ⅹが4以上であれば、カード1枚を引く。 |
ですが、《ニコル・ボーラス》は《迷える魔導士、ビビ》デッキに入れることができません。《ニコル・ボーラス》の固有色は青、黒、赤であり、青と赤は《迷える魔導士、ビビ》に含まれていますが、黒は含まれていないからです。
|
|
ニコル・ボーラス
伝説のクリーチャー ー エルダー・ドラゴン {2}{青}{青}{黒}{黒}{赤}{赤}
7/7
飛行
あなたのアップキープの開始時に、あなたが{青}{黒}{赤}を支払わないかぎり、ニコル・ボーラスを生け贄に捧げる。
ニコル・ボーラスが対戦相手1人にダメージを与えるたび、そのプレイヤーは自分の手札を捨てる。
|
さて、この「統率者戦」なのですが、MTGの開発運営側からものすごく手厚くサポートされています。
FFコラボパック発売と同時に、4種類ものFF統率者デッキが発売されているくらいですから、今からMTGをはじめる方にもその厚遇ぶりが感じられることでしょう。
もちろん、そのくらい「統率者戦」が人気のあるフォーマットである、ということでもあります。
では、具体的に「統率者戦」がどのように厚遇されているのか、ということですが、統率者戦用のカード(統率者セットカード)が作られています。
そして、これら「統率者セットカード」は、通常セットのカードではないという扱いになります。
ゆえに、たとえ直近3年のカードであったとしても、「統率者セットカード」はスタンダードでは使用できません。スタンダードは直近3年間の「通常セット」のカードを使用するフォーマットだからです。
同様の理由で、パイオニアとモダンでも使用不可能です。その一方で、原則「すべてのカード」が使用できるレガシーでは使用できます。「統率者セット」なので、当然「統率者」でも使用できます。
箇条書き形式でまとめてみます。
【統率者セットカード】
- スタンダード ✕使用不可
- パイオニア ✕使用不可
- モダン ✕使用不可
- レガシー 〇使用可能
- ヴィンテージ 〇使用可能
- 統率者 〇使用可能
「統率者セットカード」は統率者デッキだけではなく、コレクター・ブースターにも収録されています。コレクター・ブースターというのは、ひとつ3000円程度で販売されている高額パックです。
統率者セットと通常セットとは、シンボルを見れば区別できます。
FFコラボセットの場合、FFの文字とクリスタルが描かれているのが通常セット、チョコボが描かれているのが統率者戦専用カードです。

『マジック:ザ・ギャザリング-FINAL FANTASY』通常セット(FIN)
|

『マジック:ザ・ギャザリング-FINAL FANTASY』統率者セット(FIC)
|
だんだんと、この「フォーマット」というもののヤバさが伝わってきたのではないでしょうか。近年のMTG、大変ややこしいことになっています。
統率者戦専用カードの他に、FFコラボセットには
「継承史カード」というカードもあります。
例外その2:継承史カード(=再録枠)
「継承史」カードは、MTGで人気なカードを、FFのイラストと名前で再録したカードです。
たとえば、《救済者、セフィロス》の名前直下に《偉大なる統一者、アトラクサ》と書かれていますが、これは《救済者、セフィロス》が《偉大なる統一者、アトラクサ》の再録として作られたカードであり、
ルール上、両者を同一のカードとして扱うことを表しています。
この継承史カードも通常セットとして扱われません。継承史カードは「それぞれの再録元のカードがどのフォーマットで使用可能だったのか」によって使用可能フォーマットが決まります。
そのため、継承史カードは使用可能フォーマットが一枚一枚異なります。
ゆえに、それぞれどのフォーマットで使えるカードなのか調べながらデッキを組むことになります。
さらに言えば、継承史カードに限らず、すべてカードの使用可能フォーマットを逐一調べながらデッキを組むとよいでしょう。
力業ですが、これがベストです。
一枚一枚調べながら使おう
これまで紹介してきた通り、「統率者セット」「継承史カード(再録枠)」があるため、新しいパックから入手したからといってスタンダードやモダンで使用できるとは限りません。加えて、フォーマット区分上は使用可能になっていても、個別に禁止カードに指定されているパターンもあります。
そうしたことを考慮すると、いっそ一枚一枚使用可能フォーマットを調べるようにしてしまった方がよい。初心者や復帰の方であればなおさらです。
直近3年でなくてもスタンダードで使用できる『ファウンデーションズ』、通常セットではないにも関わらずモダンで使用できる『モダンホライゾン』シリーズ、『指輪物語:中つ国の伝承』というのもあります。パックに収録されていなくても、一部の構築済みデッキのカードは「通常セット」に含まれ、スタンダードやモダンで使用できます。そういう例外もあります。
繰り返しになりますが、カードの使用可能フォーマットは、逐一調べながら遊ぶのがおすすめです。
この記事において、みなさんに一番伝えたかったのはこのことです。
フォーマット、どう調べたらいい?
データベースサイトを活用する
フォーマットを調べるのにはデータベースサイトを活用するとよいでしょう。
英語に抵抗感がなければ
「Scryfall」というサイトがおすすめです。
カード画像が鮮明で、動作が比較的軽快で、UIも洗練されており、アドバンスド検索も痒いところに手が届きます。
日本語で一番機能が充実しているデータベースサイトは、
「晴れる屋通販」でしょうか。カードの使用可能フォーマットのほか、採用デッキリストまで確認できる優れものです。通販サイトでありながら、多くの日本人プレイヤーから実用的なサイトとして使用されています。
GATHERというデータベースサイトもあり、こちらはオフィシャルのものになります。日本語ローカライズがイマイチなのですが、Scryfallよりは日本語ユーザーにフレンドリーという印象です。UIがちょっと不親切ですが、十分実用に堪えます。
デッキビルダーを活用する
デッキビルダーの中であらかじめデッキを組んでしまってから、カードを買い揃えるようにすれば、使用できないカードを誤って購入するというトラブルは避けられます。
おすすめのデッキビルダーは
「Moxfield」で、圧倒的に高性能です。デッキの一人回し機能までついています。
この手のサービスの中では抜群にレスポンシブ対応の精度がよく、スマートフォンでもPCでもスムースに操作できます。一切日本語に対応していないのが難点ですが、英語に苦手意識がないのであれば「Moxfield」一択だと思います。
日本語のデッキビルダーとしては、
「晴れる屋デッキ」が有名です。
これのすごいのは、HTMLタグでウェブサイトやブログにデッキリストを埋め込むことができるという点。noteにも対応しています。
デッキリストのカードをそのままカートに突っ込むという機能もあって、これでデッキの総額を確認できるのも便利です。この機能を使って何度かデッキリストを一括購入したことがありますが、何とも言えないワクワク感がありました。
「Moxfield」で組んだデッキを「晴れる屋」にインポートすることもできます(晴れる屋→Moxfieldも可能)
「Moxfield」で組んだデッキを「晴れる屋」で買う。あるいは「Moxfield」で組んだデッキを「晴れる屋」にインポートして、他の日本人プレイヤーにシェアするという使い方もできるので、両デッキビルダーを併用してもよいでしょう。
どのフォーマットを遊べばいいのか
初心者の方からよく聞かれるのが
「どのフォーマットをやればいいのか?」ということなのですが、はっきり言ってしまえば自分にも全然わかりません。
フォーマット人気に地域差があるからです。
「調べてみたら、自分が遊びたいフォーマットの大会が地元では全然開催されていなかった」ということも珍しくありません。(さらに悪いことには、近場に公認店がなかったなんてこともあります。下調べは大事です…)
なので、一番最初にやるべきことは、最寄りの公認店へ行って、どのフォーマットがプレイできるのか確認しておくことです。公認店は公式サイト(
https://mtg-jp.com/shop/)か、「MTGコンパニオンアプリ」で調べることができます。
…そう前置きしたうえで、私個人のおすすめのフォーマットを紹介していきたいと思います。
統率者戦
統率者戦は、「とにかくFFのカードをたくさん使って遊びたい」という方におすすめしたいフォーマットです。
「通常セット」のカードも「統率者セット」のカードも使えるので、単純に使えるカードの種類が多いのが魅力です。ということに加えて、カジュアルプレイヤーの多い「統率者戦」では、他のフォーマットではパワー不足で使えないカードでも遊ぶ余地があります。
そして何より、統率者戦は人気フォーマットであり、デッキを組んでいるMTGプレイヤーが非常に多いのがメリット。そのため、イベントやフリープレイが成立しやすい傾向にあります。
ただし、「統率者戦」は「カードゲームというよりボードゲーム」「MTGのカードを使って遊ぶ、MTGではないゲーム」と言われるほどに、MTGの中では独立したゲーム性を持っています。
「FFコラボを機にガッツリMTGをやり込んでみたい」と考えているプレイヤーにはあまり向かない選択肢だということも併せて伝えておきます。
ブラケット
「統率者戦」では、
プレイヤー相互でデッキのレベル(完成度)を擦り合わせておくことが推奨されています。その擦り合わせを円滑に行うために、MTG開発運営側から提示されている基準が「ブラケット」です。
「ブラケット」は各々のデッキを、その強さに応じて5段階のレベルに分類します。
そのブラケットを分けるひとつの指標となるのが「ゲームチェンジャー」カードで、「ゲームチェンジャー」に指定されているカードはブラケット1~2では使用禁止、ブラケット3では3枚まで、ブラケット4~5では無制限となっています。また、このブラケットのほかに「使用禁止カード」に指定されているカードもあります。
とにかく肝要なのは、イベントに参加する前にブラケットについて調べておくということです(
公式サイト解説記事)
ブラケットの擦り合わせが不十分だと、ゲームの展開が一方的になり、テーブルの空気が微妙になってしまうこともあります。
なお、「構築済みの統率者デッキは原則ブラケット2に相当する」ものだと公式よりアナウンスされています。"吊るし"のデッキを持っていった場合は「自分のは構築済みそのままだ、だからたぶんブラケット2だ」と申告するのが無難でしょう。
スタンダード、モダン
スタンダードは開催イベント数が多い、モダンはプレイ人口が多いということで遊びやすいフォーマットです。
ただし「統率者戦」と比べて圧倒的にカジュアルプレイヤーが少ないので、ある程度強いデッキを使うことを要求されます。
そのためにデッキリストを洗練していく過程で、デッキからFFコラボカードが居なくなってしまった、なんて本末転倒もあり得ます。
そう考えると、やっぱりFFファンには「統率者戦」がよさそうだな、とは思います。
シールド、プレリリース
「シールド」はリミテッドフォーマットの一種で、未開封のプレイ・ブースター6パックと基本土地だけでデッキを組んで遊びます。
カードパワーの低いカードでも活躍しやすいのリミテッドの特徴で、いろんなFFカードを使って楽しめます。
その「シールド」で遊ぶことができるのが「プレリリースイベント」で、6月6日~6月12日の期間中、各公認店舗で開催されます。
ただし、「シールド」は如実に実力差の出るフォーマットであり、なおかつ今MTGを遊んでいるプレイヤーはベテランばかりなので、初参加だとボコボコにされておしまいというのはザラにあることです。
他のカードゲームのように、数人は初心者やカジュアルプレイヤーが混じっていて、初心者でもゆるく遊べるというようなことは期待できません。強者に揉まれる覚悟をもってイベントに臨む必要があります。
なお、今回のプレリリースイベントでは、ウィザーズ・アカウントでイベントに参加したプレイヤーに特典があります
10面クリスタルカウンター、ウィザーズ・アカウント使用で一回参加ごとに1個配布
なので、プレリリース・イベントに参加する可能性のある方は、今すぐウィザーズ・アカウント(https://myaccounts.wizards.com/login)を作成し、スマートフォンに「MTGコンパニオン」アプリをインストールしてください
(当日その場でアカウントを作って、アプリをインストールして…というのは意外と間に合わないです。事前にアカウントとアプリを準備しておきましょう。)
なお、基本土地カードはショップで貸し出しされているので、自分で準備しなくても大丈夫です。(MTG運営サイドから公認店舗へと貸し出し用の基本土地が提供されているので、原則として基本土地の貸し出しはあります)
ダイスに関してはショップごとに対応がマチマチで、用意していないショップもあります。長丁場になることもあるので、軽食や飲み物の準備もしておいた方がいいでしょう。
【持っていくもの】
- 参加費(だいたい4000円、店舗により異なるので要確認)
- ウィザーズ・アカウント
- MTGコンパニオンアプリ
- スリーブ (裏面が不透明のもの、絶対に必要)
- ダイス10個くらい
- 飲み物、軽食
- 空のデッキケース(あると便利程度)
身内でのんびり遊ぶ
MTG公認店では「ウェウカム・デッキ」という構築済みデッキを無償で配布しています。
流石に無償で配布されているだけあって、デッキとしては全然強くありません。強いカードは何枚か入っていますが…
ウェルカム・デッキ(黒)に入っている《処刑者の族長、ヴラーン》は結構強い
フォーマットのことは気にせず、FFコラボパックから入手したカードでちょっとずつ「ウェルカム・デッキ」改造しながら、FF好きの仲間内で飽きるまでのんびりやっていく…そういう遊び方もいいかもしれません。
ウェルカムデッキは「パッケージの1色+ランダムな1色」で構成されています。プレイヤーどうしでデッキの色が違うことが、仲間内でのカードトレードのきっかけになったりとか、そういう楽しさもありそうです。
ただ、この遊び方には
「仲間が必要」という、とても根本的な欠点があります。
メジャーなコンテンツならともかく、今のMTGは随分マイナーなコンテンツになってしまっていますから、今から一緒に遊んでくれる仲間を集められるとは限りません…
マジック・リーグ
上で紹介したような、
「のんびりとしたマジック」をお店でできるのが
「マジック・リーグ」というイベントです。
プレイ・ブースター3パックと基本土地だけで30枚デッキを組み、お店に居合わせたマジックリーグ参加者どうしで対戦をして遊びます。
(偶然参加者どうしが居合わせるというのは稀なので、店舗側が集まる日時を指定するのが慣例化しているようです)
一回対戦するたびに、
「現行のスタンダード範囲のプレイ・ブースターを購入して、デッキを強化する権利」を獲得します。これでデッキをチビチビ強化していくわけですね。
一か月区切りのシーズンで開催され、シーズン終わりにデッキをリセットすることになっています。
まさに「小学生の頃に遊んだTCG」という感じで、惹かれる開催内容なのですが、
- 開催店舗が非常に少ない
- そして開催されていたとしても人が集まるかわからない
という非常にシビアな課題を抱えています。
ただ、こういうイベントもあるのだと知っておいて損はないでしょう。
2025年6~7月はMTGとのタイアップで、特殊な規定で開催されるとのことです。詳細は
こちらからご確認ください。
FFxMTGコラボを楽しみたいFFマニアたちの交流の場として理想的なイベントだと思うのですが、実際のところ人は集まるのでしょうか。
「人が集まるのであれば」という条件付きで、おすすめしたいイベントです。
なお、マジック・リーグではプレリリースのように基本土地が貸与されるわけではありません。何かしらの方法であらかじめ基本土地を用意しておく必要があります。
晴れる屋で基本土地100枚セット(各種20枚ずつ)というのを販売しているのですが、これを買っておけば二人分の基本土地は賄えると思います。
準備物としては、以下のものがあればよいでしょう。
※6月、7月開催のタイアップイベントの内容によっては、他に必要なものが生じたりするかもしれません。
【持っていくもの】
- 2000円(初期デッキ構築費用)
- 700円以上の資金(追加パック購入費用)
- ウィザーズ・アカウント
- MTGコンパニオンアプリ
- スリーブ (裏面が不透明のもの、絶対に必要)
- 基本土地各10枚ずつ
- ダイス10個くらい
- 飲み物
MTGのルールを知りたい
冒頭で
「ルールよりもフォーマットのことを先に知っておくべき」だと言いましたが、そうはいってもルールの知識も大切です。
とくにプレリリースイベントはタイトなタイムスケジュールで進行するところが多いので、予習しておいた方が安心して臨めます。
MTGのルールを知りたい方は、軽く「MTGアリーナ」(アプリ版)を触ってみることをお勧めします。ちょっと勇気が必要ですが、「初心者体験会」などに参加するのもよいでしょう。
公式ティーチング動画などもありますが、率直に言ってしまうとイマイチわかりづらいです。
やっぱり、実際にプレイしてみるのが一番だと思います。
MTGのルールはシンプルにまとまっていて、意外とわかりやすい作りになっています。やってみれば「こんなに簡単なものだったか」と拍子抜けるかもしれません。
あえてここで説明することがあるとするならば、
「クリーチャーからクリーチャーへと直接攻撃できない」ということでしょうか。クリーチャーが攻撃できるのは、対戦相手と、一部のオブジェクトだけです。
そういうルールのTCGは珍しいので、初心者の方が高い割合で勘違いしてしまいます。「クリーチャーはクリーチャーを直接攻撃できません」などとは当然ルールに書かれていないので、なおさら混乱が生じるようですね。
今回はここまで
書いておきたかったことは大体書けたので、今回はここまでにしておきます。
いまからMTGをやってみたい方、あるいは初心者にレクチャーしたいと考えている方への一助となったならば幸いです。
この記事を共有する
広告
関連記事